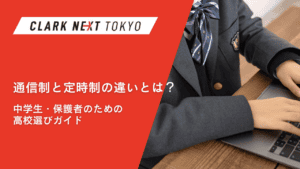不登校でも高校受験はできる?|内申点・欠席日数の壁を超える進学戦略と新しい選択肢


不登校でも高校受験は可能です
「うちの子は中学校に行けていないけど、高校には行けるの?」
「内申点や欠席日数が多くて受験できないのでは?」
そう不安を感じている保護者の方は多いと思います。
しかし実際には、不登校でも高校受験のチャンスはあります。
内申点や欠席日数にハードルはありますが、制度を正しく理解し、戦略的に動くことで進学の道は大きく開けます。
1. 不登校の現状と進学率(最新データ)
文部科学省が公表した「問題行動・不登校調査」(2024年度)によると、
全国の小中学校で30日以上欠席した不登校の児童生徒は35万3970人にのぼり、
前年度から7488人(2.2%)増加しました。
これは12年連続の増加で、過去最多を更新しています。
この10年間で、不登校の児童生徒は
- 小学生が5.5倍
- 中学生が2.2倍
に増加。
内訳は、
- 小学生:13万7704人(前年度比5.6%増)
- 中学生:21万6266人(同0.1%増)
で、児童生徒全体の3.9%、つまり26人に1人が不登校という現状です。
また、不登校の理由として学校側が把握しているものは、
- 「やる気が出ないなどの相談」:30.1%
- 「生活リズムの不調」:25.0%
- 「不安・抑うつ」:24.3%
- 「学業不振・宿題の未提出」:15.6%
- 「友人関係をめぐる問題」:13.2%
とされ、生活リズムの乱れや心理的な不調が主な原因になっています。
特に年間90日以上欠席する長期不登校は全体の54.2%を占めており、
コロナ禍以降、休むことへの抵抗感が薄れたことや、保護者の意識変化も影響していると分析されています。
それでも、不登校を経験した中学生の約9割が高校へ進学しており、
多様な教育制度の整備によって、子どもたちの進路は確実に広がっています。
2. 高校受験での壁:内申点・欠席日数・調査書
不登校生が高校受験を考えるうえで最初に直面するのが、内申点と欠席日数です。
内申点の影響
授業に出られず、テストや提出物が少ないと、内申点(評定)が低くなる傾向があります。
特に公立高校では、学力検査と内申書を7:3や6:4で評価する学校が多く、
内申点が不利に働くケースもあります。
ただし、私立高校では当日の学力試験を重視する傾向が強く、
「本番で実力を出せば合格できる」チャンスも十分にあります。
欠席日数の扱い
欠席が多い場合、「審議対象」として個別に判断されることがあります。
たとえば、都立高校では「3年間で30日を超える場合」が目安ですが、
欠席理由が明確であれば不合格になるわけではありません。
むしろ「自己申告書」で事情を説明することで、前向きに評価されることもあります。
3. 不登校生に配慮した入試制度
全国の多くの自治体で、不登校生を支援する入試制度が導入されています。
① 公立高校の特別な配慮
- 斜線措置(評定不能)
成績がつけられない教科は「/(スラッシュ)」と記載され、入試当日の学力検査で補完されます。つまり、「1や2」よりも有利に扱われることもあります。 - 自己申告書制度
欠席理由や生活状況を自分で説明できる書類を提出。
不登校の背景を考慮した柔軟な選考が行われます(東京都・神奈川県・埼玉県など)。 - 資料の整わない者としての選考制度
神奈川県では、欠席が多い生徒が「2年次の成績のみ」または「成績を使わない」選択が可能。
当日の試験結果や面接で判断される仕組みです。
② 私立高校のオープン入試
私立高校では「オープン入試」と呼ばれる形式があり、内申点を使わずに学力試験・面接で評価。
中学の成績に関わらず挑戦できるため、不登校経験のある生徒にも門戸が開かれています。
4. 不登校の生徒に合った高校の種類
🏫 通信制高校
- 自宅学習中心で登校は週1〜月1回。
- 登校負担が少なく、自分のペースで進められる。
- 受験は作文や面接中心。
🌙 定時制高校
- 午後・夜の登校が中心。
- 学力よりも「意欲」を重視する学校が多い。
- 年齢層が幅広く、多様な背景の生徒が共に学ぶ環境。
☀️ 全日制高校
- 平日毎日登校する学校。
- 不登校経験者向けの「チャレンジスクール」「エンカレッジスクール」なども増加。
- 私立ではカウンセラー常駐などサポート体制が充実。
5. 高校受験を成功させるための3ステップ
ステップ①:焦らず、まず心の安定を優先
保護者が焦るほど、子どもはプレッシャーを感じます。
「今は準備期間」「立ち止まっても大丈夫」と伝えてあげましょう。
ステップ②:志望校を“合う”基準で選ぶ
「どこに行けるか」ではなく、「どんな環境なら前向きに通えるか」で考えます。
不登校経験のある生徒を受け入れている高校や、個別相談が柔軟な学校も多数あります。
ステップ③:できる範囲で行動を
提出物を出す、先生に顔を見せる、テストを受ける。
ほんの少しの努力が「頑張っている」と評価され、内申書にもプラスに働きます。
6. 不登校生を支える外部サポート
- 不登校専門の塾・家庭教師:
学校に通えなくても、個別指導で学びを継続できる。 - フリースクール・サポート校:
通信制高校と連携し、学習と生活を支援。 - 出席扱い制度:
塾や家庭教師の活動が「出席」として認められることもあります。 - 親の会・支援団体:
同じ悩みを持つ親と交流でき、孤立を防ぐ場にもなります。
7. 保護者に伝えたい3つの大切な考え方
- 焦らなくていい。
高校受験の時期は子どもによって違っていい。 - 子どもの気持ちを最優先に。
「行かせる」より「行きたくなる」環境づくりを。 - 専門家の力を借りる。
医師やカウンセラーに相談することで、無理のない進路選びができる。
8. 不登校からの新しい進学先:「通信制高校」という選択肢
近年、通信制高校は「不登校からの再スタート」として注目されています。
登校日を自分で選べる柔軟性と、確実に高校卒業資格を得られる仕組みが整っています。
さらに近年では、全日スクーリング型の通信制高校も増えています。
これは「通信制の自由さ」と「全日制の安心感」を融合した新しいスタイル。
生活リズムを整えながら、自分のペースで学び直すことができます。
9. クラークNEXT高等学校なら、「不登校からの高校受験」を支えられる
クラークNEXT高等学校は、
「通信制高校の柔軟性」と「全日制のサポート体制」を兼ね備えた学びの場です。
- 全日スクーリングで通学リズムを整えられる
- 大学進学率73.2%(2024年度実績)
- eスポーツ・ロボティクス・メディアアートなどの専門分野を学べる
- W担任制によるきめ細やかなサポート
高校受験に不安を感じる生徒も、
「通いたい」と思える学びの環境で、再スタートを切ることができます。
まとめ:不登校でも、進学の道は必ずある
不登校は、子どもの将来を閉ざすものではありません。
高校受験に向けて一歩を踏み出す時期は、それぞれ違っていいのです。
「この子にはこの道がある」
そう信じて、焦らずゆっくり進むこと。
その選択が、やがてお子さんの未来を大きく変えます。