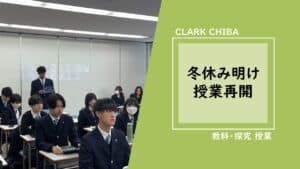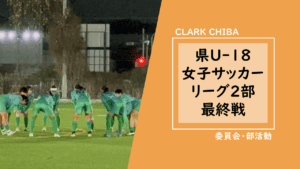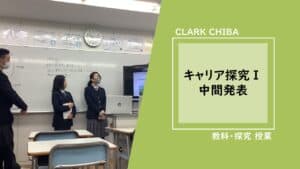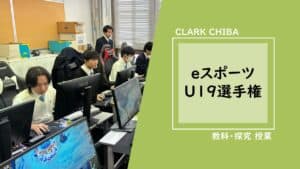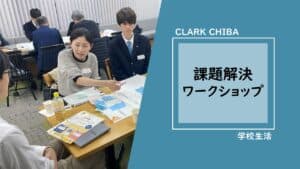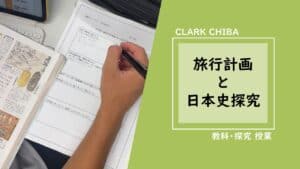「知らなかった」が「もっと知りたい」に変わる授業
文学の世界を旅するように
2025年5月14日、クラーク記念国際高等学校千葉キャンパスの1年生が国語の授業で「文学史上の人物新聞」の作成に取り組みました。タブレットを片手に、文学史に登場する歌人や詩人、小説家について調べ、グループで新聞形式にまとめていくこの授業。最初は「知らない人ばかり…」と戸惑いながらも、調べを進めるうちに、教室には自然と笑顔と熱中の空気が広がっていきました。

【新聞製作の様子】
興味の入口をつくることから始めよう
今回の授業は、高校で初めての国語の授業の一環として実施されました。目標はシンプルで明確で「文学史って面白いかもしれない」と、生徒たちに感じてもらうことです。
授業を担当した教員は「最初は“国語苦手”という声もありましたが、まずは楽しむこと、調べることを通じて、自分なりの関心を持ってもらうことが狙いでした」とのことで、従来の“覚える文学史”から一歩踏み込み、人物の背景や時代の空気を想像する“感じる文学史”への入り口として、この課題が設けられました。
タブレットで広がる、文学との距離感
当日は、教員が提示した文学史上の人物(与謝野晶子、宮沢賢治、芥川龍之介など)から各グループが1人を選び、調査を行いました。インターネット検索やデジタル資料を活用しながら、年表や作品、エピソードなどを集めていきました。
その人が生きていた時代
どんな背景で作品が書かれたのか
生徒たちは初めて知る情報に目を輝かせながら、グループ内で意見を交わしていきました。

【写真:グループワークで調べ学習を進める生徒たち】
この人、今だったら炎上してるかも…?
生徒たちの感想からは、文学史が一気に“遠い過去のこと”ではなくなった様子がうかがえました。
ある生徒は「写真で見るより年が若い人だった」「この行動、今だったら炎上してるかも」と笑いながら話してくれました。時代背景や価値観の違いに気づき、現代との比較を通じて、より深い理解へとつながっていったようです。
さらに、調査中の会話では「この詩、今でも使えそうじゃない?」「なんか共感できる」といった声も。言葉を通じて人の思いに触れる体験が、国語の世界をより身近に感じさせてくれていました。
興味の“種”がまかれた
今回の活動を通して、国語が「読む・書く」だけの教科ではなく、時代や人を知る入口になることを実感した生徒も多かったはずです。
「最初は興味がなかった人物に夢中になって取り組んでいた」「調べていくうちにどんどん面白くなっていった」と教員が語るように、生徒たちが主体的に学ぶ姿勢を見せていたことが、何よりの成果でした。

【写真:完成した新聞作品の一部】
今後もこのような学びを重ねながら、生徒たちが“知る楽しさ”に出会い、自らの言葉で発信していく力を育んでいってくれることが期待されます。