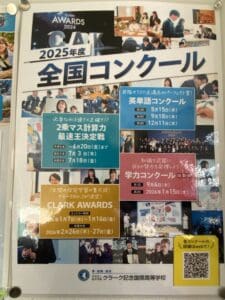【学習】 「理科(生物基礎)」授業 ~DNAの二重らせん構造ってどんな意味があるのだろう?~
1年生の「理科(生物基礎)」では、遺伝に関する学習をしています。その中で出てくるDNAについてですが、二重らせん構造ということは知られていても、その構造にどんな意味があるのかといったことはあまり知られていません。今回の授業では、DNAを構成する基本単位であるヌクレオチドの模型を並べ、二重になっていることの意味を考えました。
初めはヌクレオチドの模型を眺めるだけで、アイデアが湧かない生徒も多くいましたが、「形に注目して、何かできることはないだろうか?」という問いかけから、AとT・GとCのヌクレオチドがぴったりはまる形だと気づき、どんどんつなげて並べることが出来ました。こうした活動から、ヌクレオチド鎖が1本あれば、もう片方の塩基の配列が分かることに気づいた生徒もおり、二重になっている意味を考えることが出来ました。
さらに、ねじれたらせん構造になっている意味も考えたところ「綱引きの綱のように頑丈になる」という考えや「ねじることでコンパクトになる」など様々なメリットがある可能性についても考えることが出来ました。
クラークではこのように、教師が説明し生徒への知識の定着を図る従来型の一斉授業だけではなく、生徒自身が考え気づくことを促し、一人一人に最適でさらに学びを深めたくなるような授業を展開しています。