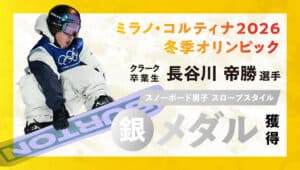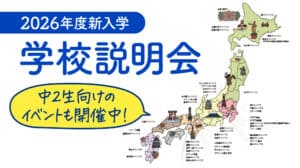これからの宇宙と地球について考える1日「クラーク宇宙の日 2025」が開催されました!

11月10日(月)、クラーク記念国際高等学校では、2回目となる「クラーク宇宙の日 2025」を開催しました。2023年11月10日に人工衛星Clark sat-1「AMBITIOUS」を打ち上げたことを記念し、毎年この日を「クラーク宇宙の日」と定め、全国のキャンパスで宇宙や地球について考える取り組みを行っています。今年は京都キャンパスをメイン会場に、全国のクラーク生がオンラインで参加しました。
宇宙を考えることは、地球を考えること
開会にあたり、吉田 洋一校長は「この宇宙の日は、単なる記念日ではありません。未来を担う私たちが、これからの宇宙と地球をどのようにしていくべきか、自分ごととして考える日です」と語り、生徒一人ひとりが自分の夢と挑戦を見つめ直す機会となることへの期待を述べられました。


宇宙米・大豆プロジェクト成果発表
今年のメインプログラムのひとつが、全国のキャンパスが取り組んでいる「宇宙米・大豆プロジェクト」の成果発表です。「宇宙でもお米を育てられるのか?」という大胆なミッションに対し、全国から選ばれた4チームが探究の成果を発表しました。


三田キャンパス まんげつもち
水稲(すいとう)と陸稲(おかぼ)の栽培環境の違いに着目し、限られた水資源での米栽培の可能性を探究。プランターで栽培した陸稲の「満月餅」が、水を節約しながらもバケツ栽培の水稲より多くの収穫量を記録し、月での米作りの実現可能性を示しました。
浜松キャンパス 未来を実らせる宇宙米
昨年度に続き2回目の登壇となった二人。今年度は水不足問題にフォーカスし、マイコス菌根菌を活用した実験を実施。一度は失敗を経験したものの、土の配合を変更して再挑戦し、マイコス菌により稲の成長が約1.5倍促進されることを実証しました。


鹿児島キャンパス 発展版!? 乾燥に強い最強米〜餅井キャンパス長におにぎりを♡♡〜
種子プライミングと植物プライミングという手法を用い、乾燥ストレスに適応できる「最強米」の開発に挑戦。一度種にカビが発生する失敗を経験しましたが、原因を分析して再挑戦。月面だけでなく、地球上の乾燥地帯での飢餓問題解決にも貢献できるものとして発表しました。
連携校大阪梅田キャンパス 宇宙米の経過報告・今後の取り組みについて
輸送費削減を最終目標に、砂の配合の割合を変えた栽培実験を実施。米の栽培では失敗したものの、サラダ大根「あやめっこ」を使った実験で砂100%の環境でも発芽することを確認。米の品種改良であやめっこに近づけることで、宇宙での米栽培の可能性を見出しました。

審査員には、宇宙タレントの黒田 有彩さん(宇宙探究部®特別顧問)、ホクレン農業協同組合連合会の菊地 修さん、山下 純俊さんをお迎えし、「失敗を恐れず挑戦し続ける姿勢が素晴らしい」「地球の食糧問題にもつながる研究」と、専門的な視点から講評をいただきました。
京都大学・山敷庸亮教授による特別講演
午前のプログラムでは、京都大学大学院 総合生存学館教授でSIC有人宇宙学研究センター代表の山敷庸亮教授による講演「コアバイオームコンセプトと月面居住 〜宇宙で生きるための挑戦〜」が行われました。


山敷教授は、ご自身の東日本大震災での福島第一原発事故の調査経験から宇宙研究への転換に至った経緯を紹介。宇宙放射線の危険性や太陽系外惑星の環境、そして宇宙移住を実現するための3つのコアコンセプト(コアバイオーム・コアテクノロジー・コアソサエティ)について解説されました。
「人間は地球上では森林と海に支えられて生きています。宇宙でも持続可能な暮らしを実現するためには、地球の自然資本をどう再現するかが重要です」と語り、アリゾナでの実験事例なども交えながら、宇宙での生態系構築の課題について詳しく説明されました。
宇宙探究部®の活動報告
午後からは、宇宙探究部®の、この一年の活動の発表が行われました。宇宙探究部®とは、2021年に発足した全国のクラーク国際の生徒で構成される部活動で、宇宙や科学技術に関心のある生徒たちが集い、宇宙に関連する様々な探究活動を行っています。
星空ライブカメラプロジェクト
まず、深川キャンパスとニュージーランドキャンパスに設置された星空ライブカメラの紹介がありました。生徒たちが自ら機材を選定し、設置作業を行ったもので、日本と南半球でそれぞれ違った星空を24時間配信で鑑賞できるシステムです。


星空写真コンテスト
次に、全国のクラーク生を対象にした星空写真コンテストの結果発表がありました。第1回の夜空・夕日・雲部門では126件、第2回のペルセウス座流星群では約200件もの応募があり、その中から選ばれた1〜3位までの写真が表彰されました。


宇宙のまなつくプロジェクト
最後に、「まなんでつくる」をコンセプトに、宇宙に関するショート動画を制作する「宇宙のまなつくプロジェクト」の紹介がありました。特別顧問の黒田有彩さんの指導のもと、生徒たちが野辺山天文台、星空ライブカメラ、ふたご座流星群など、多様なテーマで1分間の動画を制作し発表しました。
発表者の生徒からは「動画制作を通して情報の信憑性を調べることで、学びが深まった」「見てくれる人にワクワクを伝えるための工夫を考えることが難しかった」といった感想が聞かれました。


全国のクラーク生の宇宙への熱い探究心が感じられた「クラーク宇宙の日 2025」。プロジェクトの内容は多種多様ですが、そこに共通するのは「地球と人の未来をどう描くか」という問いでした。
生徒たちの活動は、学問の枠を越えて、科学・環境・生命と向き合う“生きた学び”の場となっています。生徒たちの今後の挑戦を、これからも応援よろしくお願いします。
宇宙教育プロジェクト
2021年に始まった宇宙教育プロジェクト。宇宙をテーマにしたクラーク独自の探究学習プログラムを作る目標を掲げ、生徒が実際に宇宙に触れる機会を創出すべく、生徒主体の人工衛星の企画・運用プロジェクトに始まり、現在も様々なプロジェクトが進行中です。